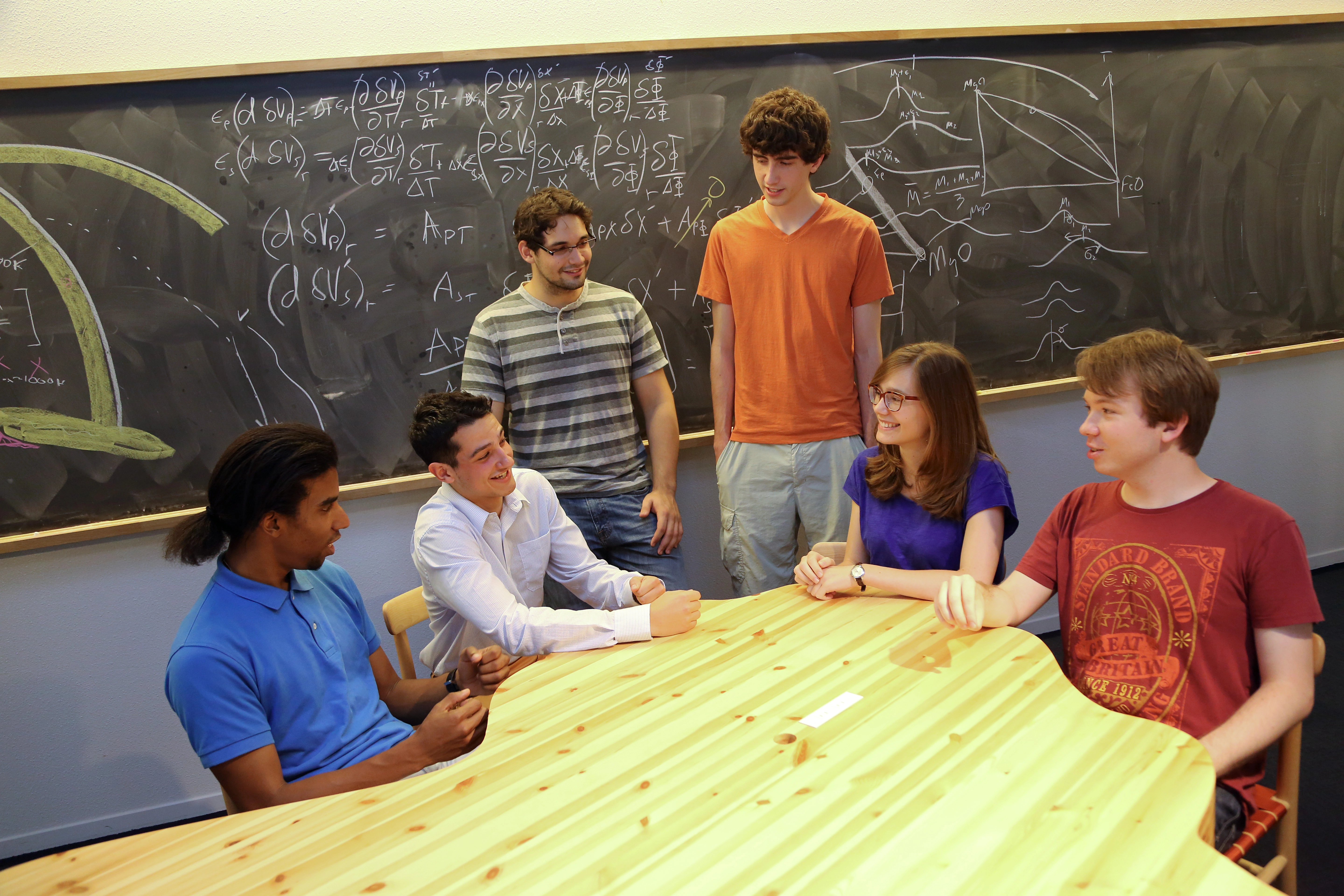日本の研究が、世界にどう届いているか知っていますか?
もちろん、論文を発表することで世界の研究者に成果を発信しています。でも実は、論文を発表するだけでは、研究成果はなかなか国際的に浸透しないことも事実です。
そこで、研究成果を効果的に世界の隅々へ届ける手段として、学術雑誌(ジャーナル)の通常号に論文掲載するのでなく、特集号を企画して載せる方法があります。特集号制作は、日本の研究者にとってはまだまだ挑戦の余地のある戦略です。

東京科学大学(Science Tokyo)の粂昭苑(くめ・しょうえん)教授は、この特集号づくりに2023年の夏に挑戦しました。そして、約2年の歳月をかけて、2025年6月に完成させました。この特集号づくりの舞台裏で、どのような協力や活動があったのかを語ります。
特集号づくりに挑戦を決めた理由は何ですか?
粂 特集号とは、特定のテーマにフォーカスして複数の論文を集めた号のことです。例えるなら、「博物館の特別展」みたいなものです。
特集号を制作する際には、企画・運営などをゲスト・エディターと呼ばれる編集責任者が担当しますが、今回は、その役割を私が担当することになったのです。「博物館の特別展」を任されたら、責任重大だと思いませんか?特集号の学術テーマに関連した広範な知見が要求されます。
実は、残念ながら、私が関わる分野では、特集号を制作したり学術雑誌のエディターを務めたりすることにはそれほど積極的ではありません。特集号制作のためには、企画・立案、投稿者のリクルート、査読のマネジメントなど様々なスキルが求められるからです。また、制作時間がとられる割に、その実績は必ずしも研究の実績ほど評価されない傾向にあるのです。
今回の特集号制作のお誘いを最初にしてくれたのは東京科学大学のURA(後述)および彼らと連携する二つの研究機関(金沢大学と自然科学研究機構)のURAでしたが、とても前向きで、かつ、深い情熱をもって科学研究の支援をしています。

「日本の研究者はもっと世界に発信していくべきです。ゲスト・エディターとして特集号を一緒につくりませんか」という提案を受けたとき、研究の最前線を自分たちで企画して発信することで、東京科学大学の広報になるのであればと、やりがいを感じました。
特集号のテーマはどうやって選んだのですか?
粂 私自身は、消化器官(膵臓・肝臓・腸)を試験管内で再生し、創薬や医学応用への展開を目指して研究していますが、分野としては限定されています。一方で再生医療という点では、世界の人々が注目するテーマです。そこで、今回の特集号では、再生医療の観点から研究対象をより幅広く設定し、細胞・組織・臓器などの多岐にわたる視点で世界の最前線の研究成果を集めた特集号にしようと思いました。
ただし、テーマが決まればどのジャーナルでも特集号を制作させてくれるわけではありません。また、できるだけ多くの方々に論文が届くように、良いジャーナルに掲載したいとも思います。すると、出版社が発行する数多くのジャーナルの中から、わたしたちの提案に賛同してくれる学界評価の高いジャーナルを探す必要があり、ジャーナル選定がとても重要です。
今回は、URAが中心になって、積極的にエルゼビア社と交渉し、European Journal of Cell Biologyというジャーナルで特別号を制作するところまで準備を進めてくれました。

私自身は交渉に直接関与しませんでしたが、その大変さは十分に感じました。何と言っても、交渉相手は外国にいるジャーナル・エディターです。時差を乗り越えて、英語でのオンライン会議を何度も重ねる必要があります。この部分をURAが一手に引き受け調整してくれたので私自身は本当に助かりました。
その結果、多様な投稿論文とともに、異分野融合や新規材料の応用など、幅広い研究の内容を掲載した特集号が2025年6月に完成しました。2年弱かけて完成したとき、「やっとここまで来た」という達成感と喜びを感じ、そして、本当に安堵しました。
特集号ではどのような論文が掲載されたのですか?
粂 この特集号のタイトルは、最終的に「Advances in cell, tissue, organ engineering, and organoid technology(細胞・組織・臓器の工学的応用とオルガノイド技術の最前線)」となりました。オープンアクセスジャーナルなので、興味のある方は誰でも無料で読むことができます。専門的な内容ですが、最近では一般読者向けの内容要約を頼めるAIツールもあるので、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思っています。
粂 大雑把にいうと、この特集号では、幹細胞から作られるオルガノイド(英語で「臓器もどき」の意味。臓器のような形と機能を持つ立体的な細胞組織モデル)を用いた最新の研究成果を集めました。疾患モデル化や創薬、個別化医療など幅広い応用が取り上げられていますが、中でも注目は、遺伝子改変マウス大腸がんオルガノイドを使って、腫瘍の進行や免疫環境を再現した研究です。これは、免疫チェックポイント阻害剤(日本の科学者、本庶佑(ほんじょ・たすく)さんが開発した免疫のブレーキを外してがんを攻撃させる薬:2018年ノーベル賞受賞)の効果が出にくい大腸がんの理解に貢献しています。また、脳オルガノイドの意識形成の可能性や遺伝疾患の修復研究など、倫理や先端医療に関わる議論も含まれていて、ユニークな切り口での特集号ができたと思います。
URAと研究者は一緒に仕事をするのですか?
粂 URA(ユニバーシティー・リサーチ・アドミニストレーター)という役職は2011年頃から始まった文科省URA育成事業とともに大学に設置され始め、現在では多様な研究支援・推進業務を担っています。たとえば、外部資金獲得支援や、知財管理、国際共同研究・融合研究支援や研究広報など、非常に多岐にわたっています。東京科学大学でも、URAという肩書のある職員は100名を超えます。しかし、自分自身がURAと実際に協働するのは今回が初めてでした。
今回の特集号制作では、URAが企画提案、投稿候補となる研究者のリストアップや出版社との調整、研究者同士のワークショップの企画・運営、ファシリテーション(議論を円滑に進める進行役)などを担当してくれました。研究者が研究そのものに集中できるようにという配慮によるものです。舞台裏で支えてくれている舞台監督みたいですよね。URAを、単なる研究支援者としてではなく、「研究推進のパートナー」として迎えることのポテンシャルの高さを実感しました。
今回の経験を通じて得たことや、今後への展望をお聞かせください
粂 一言で言えば、新鮮で興味深い経験でした。こんな活動もできる、という新たな発見だったかもしれません。特集号の発行にあたっては、もちろん、論文を厳正に掲載審査し質を担保する手間も増えますし、通常では手に取らないような種類の論文にも目を通す必要がありました。しかし、多様な研究の切り口で再生医療研究に取り組む世界最前線の研究者(投稿者)とのやりとりが有意義でした。またジャーナル・エディターとのパイプも太くなりました。
先にも触れたように、ゲスト・エディターという役割は、確かに大変です。作業が多く責任が伴うにも関わらず、その評価に必ずしもつながるとは限らないからです。でも、研究者として世界の最前線の研究成果の発信現場に身を置くことは、何にも代えがたい魅力があります。

今回のようなURAとの取り組みにもっと多くの日本の研究者が挑んでいけば、より多くの研究者がゲスト・エディターを引き受けることにもつながり、国際的な研究ネットワークの中で日本の存在感は確実に高まるでしょう。今後もこうした特集号を起点のひとつとして、日本の研究成果が世界に力強く発信され広がっていくことを期待しています。
そして、今回の事例でも見ていただけたように、日本の研究が世界に届く瞬間には、研究者だけでなく、多くの人の力と想いが重なっています。そんな現場に立ち会えた今回の経験を、今後も次の発信につなげていきたいと思います。
取材日:2025年6月23日
お問い合わせ先
研究支援窓口